「あえて管理職にならない」トレンドの広がり~次世代リーダーのパイプラインの再構築~

管理職を目指さない若手の増加——企業のリーダーシップを揺るがす大きな変化
いま、組織のリーダーシップのあり方が大きく変わりつつあります。優秀な若手社員や次代を担うリーダー候補者が、従来のように管理職への昇進を目指さない傾向が、ますます顕著になっているのです。
この傾向はすでに現実の課題となっており、MSC/DDIの「グローバル・リーダーシップ・フォーキャスト2025」では、人事担当者の80%が自社のリーダーシップ・パイプラインに不安を抱いていると報告されています。経営層の間でも同様の懸念は広がっており、「次世代リーダーの育成」が最重要課題の一つとして挙げられています。
こうした不安には明確な背景があります。Z世代は、他の世代と比べて1.7倍の確率で、自身のウェルビーイングを守るためにリーダー職を避ける傾向が見られます。この現象は「Conscious Unbossing(あえて管理職にならない)」、つまり管理職離れと呼ばれ、すでに脆弱化しつつあるリーダーシップ・パイプラインをさらに脆弱化させる恐れがあります。 では、人材開発部門は「管理職離れ」という現象をどのように捉え、どう対応すべきなのでしょうか。そして、変化するリーダーシップのあり方に適応しながら、確固たる次世代リーダーのパイプラインを築くには、どのような取り組みが求められるのでしょうか。本コラムでは、その鍵となる4つのアプローチについて詳しく解説します。
管理職離れとは
「管理職離れ」とは、若手社員が従来のように管理職への昇進を目指すのではなく、あえてその道を選ばない傾向を指します。こうした選択の背景には、職場における価値観の変化があり、特にZ世代(1997~2010年生まれ)は、リーダーシップや組織の階層構造に対する考え方がこれまでとは大きく異なってきています。
あえて管理職にならないことを選ぶ理由を理解する
職場環境の変化とともに、人々の価値観や期待、キャリア観も大きく変わりつつあります。特にZ世代で「あえて管理職にならない」という選択をする人が増えている背景としては、以下のような理由が挙げられます。
自由を求める働き方への志向

リモートワークやハイブリッド型勤務の普及により、若手社員には早い段階から「自分の時間や働き方を自由にコントロールできること」が当たり前だと感じている人もいます。そのため、オフィス出社の方針や厳格なルールの再導入に対して、「なぜ従来の階層型の管理が必要なのか」と疑問を抱く人が増えました。「成果さえ出せば、いつ・どこで・どのように働くかは自由であるべき」と考える傾向が強まっているのです。
また、ギグエコノミー(フリーランスなどの立場で、単発もしくは短期の仕事を請け負う働き方)やクリエイタープラットフォーム(個人のクリエイターがコンテンツやスキルを提供したり、ユーザーと交流したりできるサービスやサイト)の発展により、本業の経験や知識を活かして新たなキャリアを形成する働き方(ポートフォリオキャリア)や副業の選択の幅も広がりました。若手社員にとって「一つの企業に依存しない働き方」は現実的な選択肢なのです。このような経済的な柔軟性は、従来の管理体制に対する抵抗感を強め、自律的なキャリア形成を志向する要因となっています。 さらに、Z世代は「人を管理するスキルを磨くよりも、自分の専門性を高めることを優先したい」と考える傾向があります。これも、管理職を目指さない理由の一つです。
ワークライフバランスの重視

管理職のストレスは、私たちの単なる思い込みではなく実際に、これまで以上に増しています。MSC/DDIの調査によれば、71%のリーダーが、現在の役職に就いてから大幅にストレスが増加したと実感しており、自らの責務をきちんと遂行するための時間が確保できていると感じているリーダーはわずか30%です。
こうした状況を目の当たりにした若手社員が「管理職になることは意味があるのか?」という疑問を抱くのはごく自然なことです。まるで将来の自分たちの姿を見ているようで、「こんな働き方はしたくない」と考えるようになっているのです。
成長への投資が感じられない

「誰でも代わりがいる」といった考え方をもつ組織もありますが、こうした姿勢は管理職離れを防ぐどころか、むしろ加速させる要因になります。
組織が研修や育成の予算を削減する一方で、他の分野に積極的に投資していると、従業員にはその優先順位が明確に伝わります。そして、「会社が自分に投資しないのなら、自分も尽くす必要はない」と考えるようになります。その結果、表面的には業務をこなしていても、精神的には組織から距離を取るようになります。
これを裏付けるデータもあります。ハイポテンシャル人材の退職リスクは以下のように高まるとされています。
- 成長の機会がないと感じた場合、翌年に退職する確率が3.7倍
- 昇進のスピードが遅いと感じた場合、翌年に退職する確率が3.1倍
さらに、多くの組織が研修プログラムを提供していますが、その内容は画一的であったり、時代遅れのスキルに偏っていたりすることも少なくありません。特に、新しいテクノロジーや革新的な働き方に関心をもつ若手社員にとって、こうした研修は将来のキャリアに役立つとは思えず、結果としてエンゲージメントの低下を招いてしまいます。
パーパスに沿った仕事を求めている
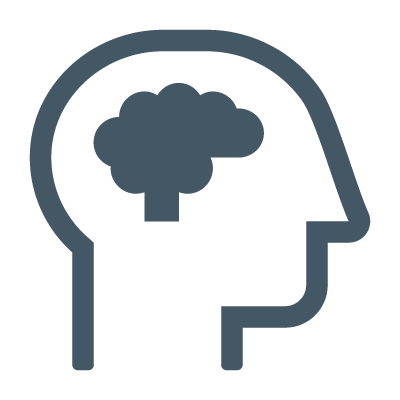
Z世代は、仕事を単なる「業務」ではなく、「自分の価値観の延長線上にあるもの」として捉えています。そのため、自分らしく働ける環境や、自分の信念に沿ったミッションに貢献できる場を求めています。 つまり、「あえて管理職にならない」という姿勢は、単にリーダーシップを拒否しているのではなく、「従来の管理システムがうまく機能していない」と感じていることの表れです。これは組織や人事担当者にとって、次世代のリーダーシップや組織文化を見直す絶好の機会でもあるのです。
管理職離れに見られる主な兆候
- リーダー職志望者の減少:ハイポテンシャル人材であっても、管理職への昇進を辞退し、現在の職務にとどまる選択をするケースが見られます。
- 専門職志向の高まり:若手社員の多くは、チームを率いるよりも、専門分野でより高いスキルを身につけたり、専門性をさらに追求したりすることを望んでいます。
- 階層型マネジメントへの反発:Z世代は、公式な権限に基づくリーダーシップよりも、影響力を通じた自発的なリーダーシップを好み、従来の指揮命令型の組織構造に対して抵抗を示すことがあります。
- ポートフォリオキャリアの選択:一つの企業での長期的な出世を目指すよりも、複数の仕事やプロジェクトを掛け持ちしながら自由に働く「ポートフォリオキャリア」を選ぶ若手社員が増えています。
管理職離れが組織に与える影響
若手社員の管理職離れの傾向は、短期的および長期的な課題を引き起こします。短期的には、若手社員のモチベーションの低下や離職率の上昇が懸念されます。長期的には、リーダー人材のパイプラインが上位層・下位層ともに崩壊するリスクが高まります。
上位層では、ベビーブーマー世代が次々と定年を迎え、これまで以上に速いペースで、経営幹部層の空席が増加しています。一方で、Z世代を中心に、従来の管理職への道を敬遠する傾向が強まっており、初級管理職の候補となる人材は減少しています。
この結果、現職のリーダー、主にX世代とミレニアル世代は、後継者不足の中で上級管理職や経営幹部職への昇進を余儀なくされる状況にあります。
これは単なる数の問題ではありません。現在、多くのリーダーシップ開発プログラムは、もはや時代にそぐわない「パイプラインモデル」に基づいて設計されています。これらは、「優れた業績を上げた人材が自然に管理職を目指す」という従来のキャリア形成を前提としています。しかし現実には、若手社員はこの道を選ばなくなっているのです。そのため、組織は人材の育成と定着の方法を根本的に見直す必要があります。人材開発部門に求められるのは、単に空席を埋めることではなく、次世代の価値観に合う、新たなリーダーシップのビジョンを描くことです。 では、人材開発部門はどのようにして、その新しいビジョン構築すべきなのでしょうか?
組織がより魅力的なリーダーシップのビジョンを策定する方法
1. パーパスを推進するアンバサダーを育成する

管理職離れへの対応として、リーダー自身が「パーパスを推進するアンバサダー」となり、チームメンバーが仕事に意義を見出せるよう支援することが重要です。特にZ世代にとって、パーパスは単なる付加価値ではなく、キャリア選択における重要な判断軸となっています。人は自らの仕事に意義を感じられれば、リーダーとして成長する意欲も自然と高まります。
人材開発部門は、リーダーが明確な目的意識をもち、それをチームに適切に伝える力を養えるよう支援すべきです。そのためには、リーダーは、チームに響く形で組織のパーパスを語る、ストーリーテリングスキルを高める必要があります。 また、リーダーが高いEQを身につけ、職場における価値観や充実感、影響力についてメンバーと意味のある対話ができるようになることも重要です。従業員が組織の大きな使命とのつながりを実感できれば、リーダーの役割がより魅力的に映り、管理職への抵抗感は薄れていくでしょう。
2. ウェルビーイングを支援する

管理職離れを防ぐには、リーダーの役割に対する新たな捉え方を提示する必要があります。そのカギとなるのが、ウェルビーイングを最優先に考えることです。組織は、リーダーが健全かつ持続的に成果を上げられるよう、心身の健康とパフォーマンスの両面を支援しなければなりません。
この変革は、トップマネジメントの行動から始まります。リーダーには、以下のようなことが求められます。
- 勤務時間内のみのメール送信
- 現実的かつ公平な期限の設定
- デジタル機器を完全にオフにする時間を確保し、それを周囲にも奨励
こうした行動は、成果だけでなくウェルビーイングも重視する組織文化の基盤となります。
さらに、リーダーが弱さを見せられる風土や心理的安全性が確保された職場環境を整えることも重要です。リーダーが安心し、支えられていると感じる環境があれば、長期的に活躍できるだけでなく、次世代を育てる原動力にもなります。
3. ハイポテンシャル人材の育成方法を再構築する

今日の若手社員は、スキル開発に対して異なる視点をもっており、「組織での昇進」よりも「個人の成長」に重きを置く傾向があります。この意識変化に対応するには、人材の特定と育成の方法を抜本的に見直す必要があります。
人材開発部門は、「誰にポテンシャルがあるのか」ではなく、「誰が学びを通じて成長を加速できるか」という視点をもつことが重要です。ポテンシャルは固定された資質ではなく、行動・学習・経験によって開花する能力です。人がどのように学び、適応し、進化していくかに焦点を当てることで、若手社員の価値観に共鳴しつつ、ビジネスニーズにも応える本質的な人材開発戦略を構築できます。
次世代リーダーを育成するために、人材開発部門は、彼らの価値観やキャリア目標に合った、柔軟でパーソナライズされたラーニング・ジャーニーを提供する必要があります。そのために、以下のような取り組みが求められます。
- アセスメント:自分の強みや成長領域を客観的に把握するための診断
- シミュレーションとコーチング:将来の役割や課題に備えるための方法
- ストレッチアサイメント:新たな責任や広範な役割に挑戦する機会
- 公式学習とスキル開発:現在または将来の役割に必要なスキルに焦点を当てた能力開発
- ピアラーニングと協働学習 :他者との学び合いを促進する場の提供
公式な能力開発プログラムが減少し、上司の離職が増え、従来のメンター制度が機能しにくくなっている今、人材開発部門にはその役割を補完することも求められています。
「スキルを学ぶこと自体が目的」となるZ世代の傾向を踏まえ、人材開発部門は、現実的なシナリオや業務フローの中でスキル習得を位置づけ、若手社員が共感できる形で提供する必要があります。彼らがすぐに活用できるスキルや、将来のキャリアに備えるためのスキルに焦点を当てることで、より実践的な成長を促すことができます。
管理職離れは「成長を拒否している」のではなく、「より柔軟で自分に合った学び方を求めている」ことの表れです。この変化を受け入れることで、人材開発部門は、より意味のあるリーダーシップ開発の機会を創出できるのです。
4. 自由を尊重する文化を築く

次世代のリーダーを惹きつけ成長を促すには、組織全体で「自律性を尊重する文化」を構築することが不可欠です。若手社員は、決められたルールに従うのではなく、自らの意思で選び、行動できる環境を求めています。
まずは、リーダーが適切に権限委譲を行えるよう育成しましょう。リーダー自身の業務負担を軽減するのと同時に、メンバーが主体的に判断し、スキルを高める機会を確保することができます。
また、柔軟な働き方を推進することも重要です。勤務時間や働く場所の選択を可能にする一方で、チームとしてのつながりを維持する工夫も欠かせません。たとえば、集中が必要な業務は各自のペースで進めつつ、チームミーティングには積極的に参加するなど、バランスの取れた働き方が望まれます。
さらに、従業員がリスクを取ることを恐れず、挑戦できる文化づくりも必要です。失敗を学びと捉える姿勢が定着すれば、イノベーションが促進され、キャリアにおける一時的な後退も成長の一環として受け止められるようになります。 このように、「自由」と「支援」が両立した職場文化では、従業員が自分の仕事や役割に主体性をもつことができます。これは、単なる「管理職離れ」の解消にとどまらず、若手社員が自分らしいキャリアを築いていける新しいリーダーシップの在り方を示すものとなるでしょう。
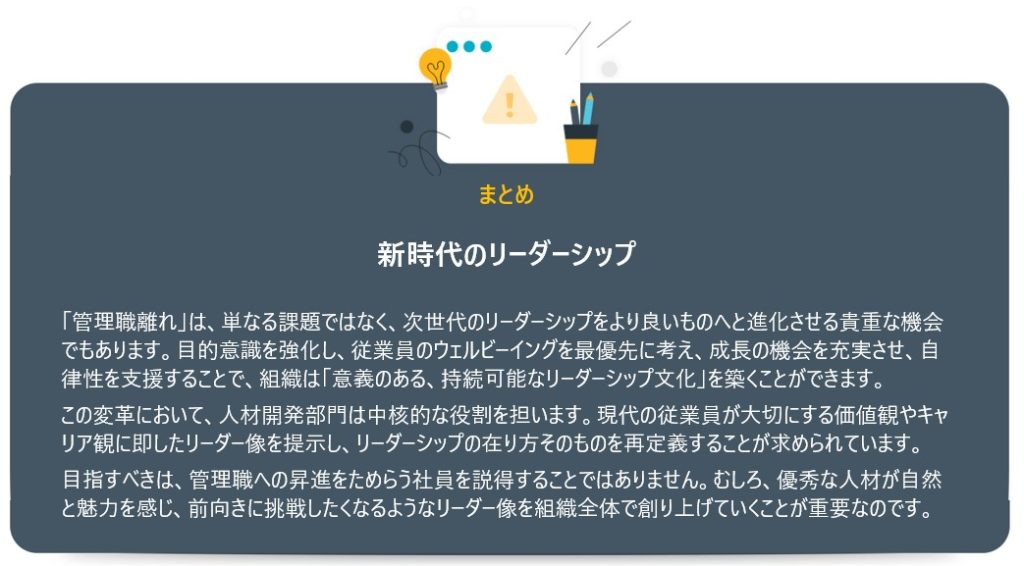
おすすめのソリューション
▼大規模調査から日本特有のリーダーシップの課題を読み解く!
グローバル・リーダーシップ・フォーキャスト2025「日本特集」
▼信頼を構築し、人とのつながりを強化するリーダーシップ開発プログラム
インタアクション・マネジメント
■執筆者:DDI バイスプレジデント ブルース・ワットPh.D.
■原文はこちら
